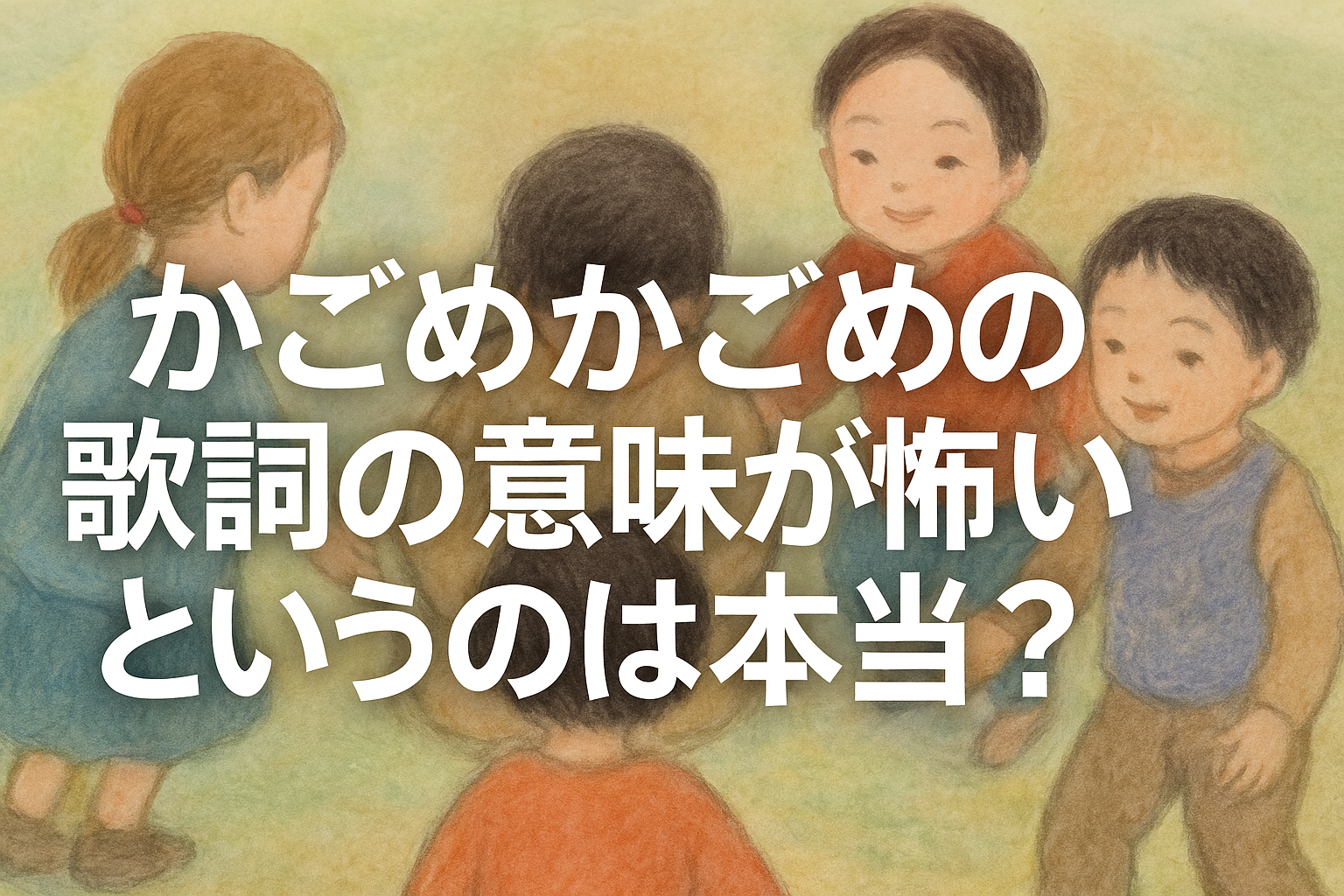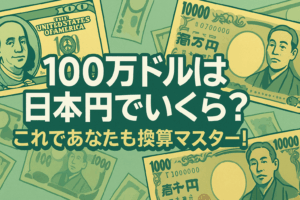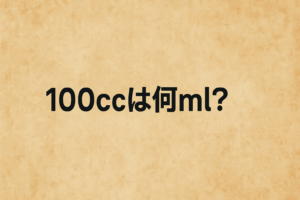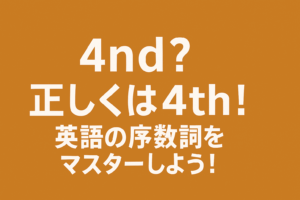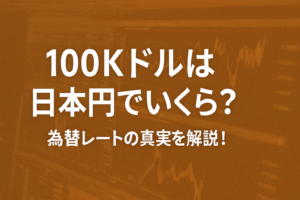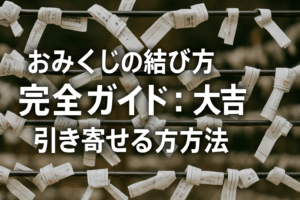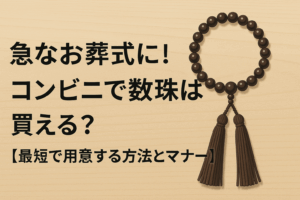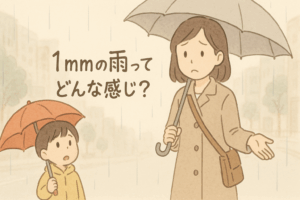「かごめかごめ」の歌詞の意味が怖いと感じたことはありませんか?
子どもの頃に何気なく歌っていたこの童謡に、実は深くて不気味な意味が隠されているという説もあります。
言葉の一つひとつに謎があり、「かごめかごめ 歌詞 意味 怖い」と検索されるほど、多くの人がその真相を知りたがっています。
この記事では、さまざまな解釈や背景に触れながら、この歌にまつわる怖い説や都市伝説をわかりやすく紹介していきます。
続きを読めば、あなたの中にあったモヤモヤがきっと晴れていきます。
- 「かごめかごめ」の歌詞に込められた多様な解釈の背景
- 歌詞が怖いとされる理由や社会的・歴史的な文脈
- 妊婦・処刑・遊女などと結びつけられる怖い説の内容
- 都市伝説や逆再生などオカルト的な視点からの考察
かごめかごめの歌詞の意味が怖いとされる理由

- 「かごめ」の語源に隠された多様な解釈
- 歌詞に潜む妊婦や流産をめぐる怖い説
- 処刑と罪人の視点から読むかごめかごめ
- 遊女との関係性から見る籠目の世界
- 口減らしと社会背景が語る隠れた真相
- 子どもの遊び歌が不気味とされる理由
「かごめ」の語源に隠された多様な解釈
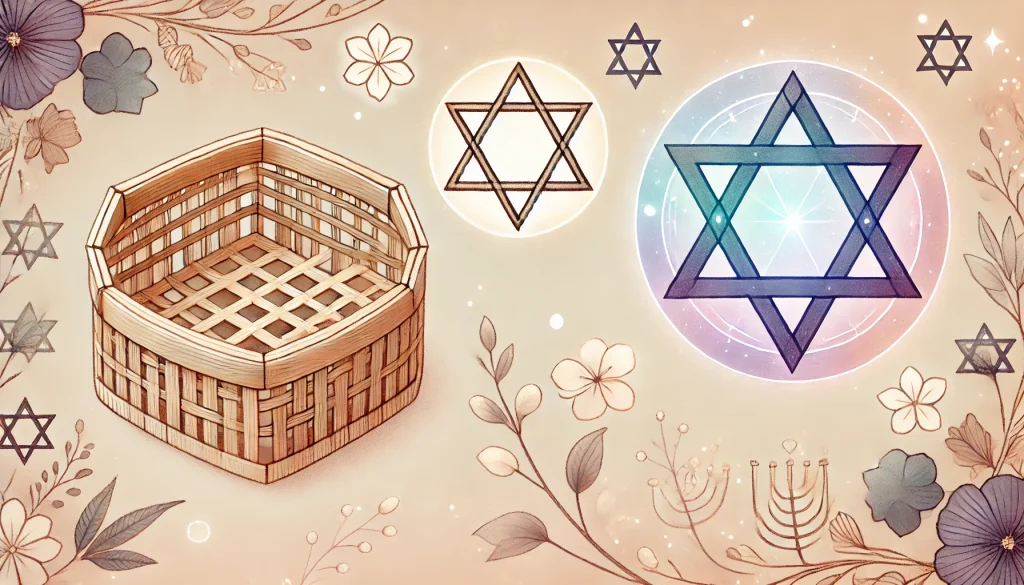
「かごめ」という言葉には、はっきりとした意味が定まっていない一方で、さまざまな視点から解釈されてきました。
単なる響きの面白さではなく、歴史や文化、宗教的な背景までもが織り込まれている可能性があるからです。
「籠の目」から見るかごめの象徴性
まず考えられるのは、「かごめ=籠の目」という説です。
これは、竹や縄で編まれたかごの模様を指しており、六角形が並んだ幾何学的な美しさをもっています。
この模様が繰り返されると、六芒星のような形に見えることがあります。
この六芒星は、日本では馴染みが薄いものの、ユダヤ文化においては「ダビデの星」として知られ、神秘的な意味を持つシンボルです。
この類似から、「かごめかごめ」にはユダヤ文化とのつながりがあるのでは、という説が生まれました。
神聖なものを封じる、あるいは守るという意味が、この幾何学模様とリンクするとも考えられています。
囲む動作と「囲め」の意味のつながり
次に、「かごめ」は動詞の命令形「囲め」から来ているとする説もあります。
これは、歌の遊び方と深く関係しています。かごめかごめの遊びでは、中央にいる“鬼”を他の子どもたちが手をつないで取り囲みます。
この構造はまさに「囲め」という言葉と一致しています。
また、「囲まれた者」としての「かごめ」は、社会的・精神的に自由を奪われた存在の象徴としても読み取ることができます。
そこには、何かを守る、または閉じ込めるというニュアンスが含まれているとも言えるでしょう。
遊郭との関係を示す「籠女」説
さらに、「かごめ」を「籠女(かごめ)」と読み替える説もあります。
これは、遊女を意味する言葉の一つであり、自由を持たず、一定の場所に囚われた生活をしていた女性たちのことを指します。
こうした女性たちの切なさや閉塞感が、かごめかごめの歌詞に込められているとする解釈も存在します。
| カテゴリー | 解釈の対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 形と模様 | 籠の目 | 六芒星に似た形。神秘的な意味と結びつけられる |
| 遊びの動作 | 囲め | 中央の鬼を囲む構造が言葉の意味と一致 |
| 社会背景 | 籠女 | 囚われた遊女の心情を暗示する可能性 |
このように「かごめ」という言葉には、さまざまな解釈が折り重なっています。
一見単純に聞こえるこのフレーズが、実は複数の文化的背景や歴史的文脈を内包しているという点が、かごめかごめの奥深さを生み出しているのです。
歌詞に潜む妊婦や流産をめぐる怖い説

「かごめかごめ」の歌詞には、妊婦や流産を暗示するような悲しい物語が隠されているのではないかという説があります。
遊び歌であるにもかかわらず、言葉の一つひとつにどこか哀しげな響きがあるからです。
胎児を表す「かごの中のとり」
「かごの中のとり」という表現は、自由のない存在を象徴しています。
このとりは、胎児のことを表しているとされ、「かご」は母親の胎内、すなわち子宮を意味していると読むことができます。
「いついつ出やる」というフレーズが続くことで、「いつ産まれるのか」という期待と不安が同居する母親の心情が重なります。
しかしこの歌では、希望に満ちた出産ではなく、「予定外に出てしまう」つまり流産を連想させるような暗いニュアンスも感じ取られます。
胎児の誕生が喜びで終わらなかったという物語が浮かび上がるのです。
「鶴と亀がすべった」が示す不吉な出来事
本来ならば吉祥の象徴である鶴と亀が「すべった」とされている点も重要です。
おめでたい存在がバランスを崩したという描写は、突然の事故や悲劇的な展開を暗示していると考えられます。
実際、この歌詞をもとに「神社の帰り道で妊婦が階段を踏み外し、流産した」という物語が語られることもあります。
そして「後ろの正面だあれ」という一節は、「誰が妊婦を突き落としたのか」と問いかけているように聞こえることから、歌詞全体が事件の追憶とも捉えられるのです。
伝承に込められた社会的メッセージ
こうした解釈は、過去の社会の姿を映し出している可能性もあります。
かつては出産が命がけであったこと、嫁姑の関係が今よりずっと厳しかったこと、そして妊婦に対する配慮やケアが十分でなかった時代背景などです。
もちろん、すべてが真実とは限りません。
しかし、童謡という形で語り継がれることによって、伝えにくい社会の影や人々の記憶がそっと残されてきたと考えることもできるのではないでしょうか。
処刑と罪人の視点から読むかごめかごめ

「かごめかごめ」という童謡には、処刑や罪人の心情を暗示するのではないかという、非常に重く陰鬱な解釈も存在しています。
この見方では、遊びの中にある構造が、死を目前にした罪人の立場と驚くほど似ているとされているのです。
囲まれた構図が語るもの
この歌では、中央にいる鬼が目を隠し、周囲の子どもたちが手をつないでその鬼を囲みます。
まさに「囲まれる」という状態そのものであり、この構図が処刑場で罪人が取り囲まれている状況と重なるという指摘があります。
特に昔の日本では、公開処刑が行われていた時代がありました。
その際、罪人は観衆や役人たちに取り囲まれ、否応なしに自らの死と向き合わなければなりません。
「かごの中のとり」という言葉も、まさに逃げ場のない状況に置かれた罪人の姿と重なって見えるのです。
「後ろの正面だあれ」に込められた恐怖
そしてもう一つ注目されるのが、「後ろの正面だあれ」という一節です。
このフレーズは、誰が自分の命を奪うのか、誰が裁きを下すのか分からないという恐怖を象徴しているとも言われています。
目隠しをされ、背後からの一撃を待つ姿は、まさに斬首される前の罪人の状態と酷似しています。
このように見ると、童謡でありながらも、言葉の裏には深い悲しみや恐怖が込められている可能性があることが分かります。
子どもたちの遊びに隠された記憶
この解釈が真実かどうかはともかく、古い時代の出来事や文化が、子どもたちの遊び歌に形を変えて残されてきたという考え方は興味深いものです。
無邪気に歌っていた歌の中に、かつての社会の痛みや歴史が込められているとしたら、それは私たちに過去を考えるきっかけを与えてくれる存在とも言えるのではないでしょうか。
遊女との関係性から見る籠目の世界

籠の中にいたのは、遊女たちだった?
「かごめかごめ」の歌詞の中に登場する「かごめ」が、遊郭にいた遊女を意味しているという解釈があります。
漢字で書くと「籠女」となり、文字通り“籠の中にいる女性”という表現です。
これは江戸時代に実在した言葉でもあり、現実の歴史とも結びついています。
この説を支持する理由の一つに、「かごの中の鳥はいついつ出やる」という一節があります。
遊女たちは、決められた囲いの中で生活しており、自由を得るには「身請け」と呼ばれる特別な買い手が現れる必要がありました。
しかしそれはごく限られた希望であり、大半の遊女にとっては叶わぬ夢だったのです。
遊郭という社会の縮図
遊郭という場所は、ただの遊び場ではなく、厳しい身分制度や経済格差の中で成り立っていた閉鎖的な社会でした。
そこにいた女性たちは、親の借金のために売られたり、幼くして連れてこられたりしたこともあり、自らの意志ではどうにもならない運命を背負っていました。
その中で「かごの中の鳥」という表現は、非常に象徴的です。
逃げることも飛び立つこともできない。そんな彼女たちの心情が、童謡の形を借りて語り継がれてきたと考えると、歌の持つ意味は一気に重くなります。
希望と諦めが交差するフレーズ
「いついつ出やる」という言葉は、文字通り「いつ外に出られるのか」を意味するものですが、この中には自由へのあこがれや、自身の境遇への諦めが混じり合った複雑な感情が感じられます。
未来が見えない不安、そしてわずかな希望を失わずにいるための祈りのようにも聞こえます。
このように考えると、「かごめかごめ」は単なる遊び歌ではなく、社会の底辺で声を上げられなかった人々の思いが、形を変えて残されたものなのかもしれません。
口減らしと社会背景が語る隠れた真相

生活苦の中にあった、残酷な現実
「かごめかごめ」が「口減らし」に関係するという説も存在します。
口減らしとは、食糧難や極度の貧困に苦しむ家庭が、生きていくために家族の人数を減らさなければならなかった悲しい選択を指します。
日本の歴史の中でも、特に農村部ではこのような現実が繰り返されてきました。
飢饉が続いた年や、年貢の負担が重くのしかかった時期には、子どもを里子に出したり、売り渡したりすることがやむを得ない判断とされていたのです。
子どもが選ばれるという残酷さ
悲しいことに、誰を手放すかを決める際に「かごめかごめ」のようなわらべうたが使われていた、という話もあります。
これが事実であるかどうかは証明されていませんが、こうした噂が存在するだけでも、その時代の悲惨さが想像できるでしょう。
選ばれる子どもたちが、自分たちの遊びの中でこの歌を口ずさんでいたとしたら…。
そう考えると、なんともやりきれない気持ちになります。表向きは明るく楽しげな歌でも、背景にあるものは非常に残酷だったのです。
表面的な楽しさと、見えない重さ
このように「かごめかごめ」は、単なる遊び歌のように見えて、実は社会の闇を内包していたのではないかという考え方もあります。
生活苦、制度、時代背景――そういったものが重なり合い、何気なく歌われていた童謡に複雑な意味が込められていたとしたら、これは偶然では済まされません。
現代では想像しにくい話ですが、かつての日本においては、家庭の中でさえ命の重さが平等でないという、厳しい現実があったのです。
「かごめかごめ」がそうした時代の記憶を伝える歌であるとするならば、それはただ怖いというだけではなく、深く考えさせられる存在でもあります。
子どもの遊び歌が不気味とされる理由

明るい曲調と不穏な内容のギャップ
「かごめかごめ」のような童謡が不気味に感じられるのは、その曲調と内容の間にあるギャップが原因です。
明るくリズミカルなメロディーに対して、歌詞の内容は曖昧で、どこか不安をかき立てるような表現が多く含まれています。
これは「楽しさ」と「恐怖」が一緒に存在しているため、心がどう反応していいのか戸惑ってしまうのです。
その結果として「なんだか怖い」といった印象を持つことにつながっています。
遊び方そのものが心理的に不安を誘う
もう一つの要因は、「かごめかごめ」の遊び方にあります。
目隠しをした鬼が、自分の背後にいる人を当てるというルールは、周囲の状況が見えない不安や緊張感を生み出します。
目が見えないということは、子どもにとっても大きな恐怖につながるものです。
さらに、誰が後ろにいるのかもわからず、それを当てるという流れは、単純な遊びの中に「見えないものへの恐れ」が潜んでいるように感じさせます。
意味が曖昧だからこその怖さ
歌詞に具体的なストーリーがなく、象徴的な言葉だけが並んでいることも、不気味さを引き立てる要素です。
「夜明けの晩」「鶴と亀がすべった」「後ろの正面だあれ」など、普通では結びつかない表現が並ぶことで、「これは何を意味しているのか?」という疑問がわき、想像力が働きすぎてしまうのです。
このような“意味の空白”は、人間にとって時に恐怖の源になります。
曖昧なもの、不確かなものは、理解できないからこそ怖いのです。
想像力が生み出す「余白の怖さ」
この童謡の持つ怖さは、はっきりとした恐怖ではなく、“何かがありそう”という想像によって作られています。
人は見えないものや意味がわからないものに対して、自分の知っている怖い話や体験を当てはめてしまう傾向があります。
だからこそ、「かごめかごめ」のような歌は、現代に至るまで多くの都市伝説や怖い説が語られ続けているのです。
童謡の中にある「余白の怖さ」は、いつの時代も人の心をざわつかせてやまないのかもしれません。
かごめかごめの歌詞の意味が怖いと言われる背景

- 呪いの歌としてのかごめかごめの側面
- 歌詞に込められた火や災厄の象徴性
- ヘブライ語から読み解く隠されたメッセージ
- 逆再生に込められた意味とその衝撃
- 六芒星と徳川埋蔵金にまつわる都市伝説
- 作者不詳の童謡が語る謎と歴史の深淵
呪いの歌としてのかごめかごめの側面

「かごめかごめ」は、子どもの遊び歌でありながら、昔から“呪いの歌”としても語られてきました。
この背景には、歌詞の曖昧さと、不思議なリズム、そして聴く人に不安を与えるようなメロディがあると考えられています。
見えない存在とつながる歌詞構造
中でも特に注目されるのが「後ろの正面だあれ?」という問いかけです。
これは遊びのルールとしては、自分の背後に立っている人を当てる遊びの一環です。
しかし、この言葉は現実的に見えない相手へ向けた呼びかけにも思えます。
まるで、霊的な存在や過去の記憶に問いかけているようにも聞こえるため、不気味さが強調されるのです。
加えて、「かごの中の鳥はいついつ出やる」という一節には、何かが閉じ込められた状態から解放されることを願う気持ちが込められているとも読み取れます。
この“何か”が魂や怨念であるとする説もあり、ただの遊び歌にはとどまらない深い象徴性を含んでいるのです。
不気味な演出が「呪い」のイメージを助長
このような歌詞の雰囲気に加え、実際の遊び方にも不穏な要素があります。
目隠しをされた鬼の周囲を子どもたちがぐるぐると回り、「だれ?」と問いかけるこの構造は、儀式的な印象を与えることもあります。
特に暗い場所で行われると、その神秘性はより強くなります。
こうした要素が重なることで、「この歌には呪術的な力があるのでは」と感じる人が出てきたのも自然なことです。
一部では「夜に歌ってはいけない」「口ずさむと不幸が起きる」といった噂が広まり、オカルト的な印象を持つ人も少なくありません。
ただの遊び歌として片付けられない深み
もちろん、現代では多くの子どもたちが何の悪気もなく「かごめかごめ」を歌っています。
しかし、背景にある言葉の選び方や演出の不思議さが、人々に「呪いの歌ではないか」と思わせる要因になっているのは事実です。
怖い意味を信じるかどうかは人それぞれですが、子ども向けの歌であっても、言葉のもつ力を改めて感じさせる一例といえるでしょう。
歌詞に込められた火や災厄の象徴性

「かごめかごめ」の歌詞には、火災や災害といった“不吉な出来事”を暗示する要素が潜んでいるという説もあります。
これは、特定の言葉の使い方や矛盾した時間表現などから読み取れるものです。
矛盾する時間表現がもたらす違和感
特に注目されるのが、「夜明けの晩」という表現です。
夜明けと晩は本来、時間軸の正反対に位置する言葉ですが、それを一緒に用いることで、現実には存在しない“あいまいで不安定な時間”が描かれています。
こうした非現実的な表現が、日常の枠を超えた世界観を感じさせ、聞く人に不穏な印象を与えているのです。
さらに、「鶴と亀がすべった」というフレーズにも注目が集まります。
鶴と亀は日本文化において長寿や吉兆を意味する存在ですが、その二つが「すべる」というネガティブな行動をとることで、不吉な予兆を感じさせる演出となっています。
火を暗示するヘブライ語解釈
ある説では、「いついつ出やる」の部分が、ヘブライ語の「火をつける」という意味を持つ言葉に似ているとされます。
このように音の響きや言葉の置き換えを通して、「かごめかごめ」全体が災厄や焼失を描いた物語であるとする解釈も存在します。
| 歌詞フレーズ | 解釈例 | 内容 |
|---|---|---|
| 夜明けの晩 | 非現実的時間 | 時空の歪みや不安の象徴 |
| 鶴と亀がすべった | 不吉な出来事 | 幸運の崩壊・転落 |
| いついつ出やる | 火の命令 | 災厄・裁きの象徴 |
このような解釈に立てば、「かごめかごめ」は災いを暗示し、時にはそれを呼び寄せる儀式的な意味合いを持つと考えられるのです。
注意すべき点と向き合い方
ただし、これらの説はあくまで一部の研究や民間の言い伝えによるもので、確固たる学術的裏付けがあるわけではありません。
そのため、過剰に不安がる必要はないでしょう。
むしろ、童謡が持つ多層的な意味や日本語の奥深さを感じる機会として、好奇心をもって向き合うのが良さそうです。
ヘブライ語から読み解く隠されたメッセージ

「かごめかごめ」の歌詞には、日本語での意味とは別に、ヘブライ語として解釈できるという興味深い説があります。
この考え方によって、歌詞の一語一語がまったく異なる意味を持ち始め、古代の宗教的なメッセージが隠されていたのではないかという仮説が展開されています。
言葉の響きから見える別の解釈
例えば、「かごめ」はヘブライ語で「囲む」を意味する言葉に近い音を持つとされ、「何を囲んでいるのか?」という問いかけに変換されることがあります。
そして「かごの中の鳥」は、神聖なものが封印された状態を象徴しており、鳥は神の使い、または聖なる守護者と見なされることもあります。
さらに、「いついつ出やる」という部分は、「取り出せ」「燃やせ」といった強い命令形の言葉と解釈され、神宝を取り出す儀式や、聖地の焼失といったストーリーが浮かび上がってくるのです。
物語として再構築される内容
この説によれば、「かごめかごめ」の歌詞は単なる遊び歌ではなく、古代の神聖な儀式を示す暗号のようなものだったという考え方もできます。
ある場所に隠された神宝を囲んで守り、必要なときにそれを取り出し、社を焼き払って新しい地へと導くという物語構造です。
以下は、ヘブライ語説に基づく構成の一例です。
| 歌詞フレーズ | ヘブライ語解釈 | 象徴するもの |
|---|---|---|
| かごめかごめ | 囲め・守れ | 神聖な宝物を囲む儀式 |
| かごの中の鳥 | 封印された神宝 | 神の使いまたは聖遺物 |
| いついつ出やる | 取り出せ・燃やせ | 儀式・裁き・移転の命令 |
謎めいたロマンと注意点
このような解釈は非常にロマンにあふれており、「かごめかごめ」が単なる遊びを超えて、深い歴史や信仰と関わっていると感じさせる魅力があります。
ただし、こうした説には明確な学術的根拠がなく、あくまで仮説の域を出ていないという点は押さえておく必要があります。
言葉の響きだけで意味を結びつけてしまうと、誤解を招く可能性もあるため注意が必要です。
とはいえ、童謡が異文化と結びつくことで、思わぬ視点や発見につながるというのは非常に面白い現象です。
一つのわらべうたが、これほどまでに広く深く、解釈を生むのは珍しいことと言えるでしょう。
逆再生に込められた意味とその衝撃

「かごめかごめ」を逆再生すると、不思議な声や意味深な言葉が聞こえるという話があります。
これは都市伝説の一種として知られており、多くの人が興味本位で再生を試してきました。
不気味な言葉が聞こえる理由とは?
再生した音声からは、「たすけて」「あけて」といった助けを求めるような言葉が聞こえると言われています。
このような声は、まるで誰かが閉じ込められているかのような印象を与えます。
歌の内容と照らし合わせると、「かごの中の鳥=囚われた存在」が何かを訴えているように思えるのです。
この現象は、ただの偶然やこじつけだと感じる人もいるかもしれません。
しかしながら、こうした“聞こえてしまう”現象には、心理的な仕組みも関係しています。
人は意味のない音からでも、何か意味を見つけ出そうとする傾向があり、これを「パレイドリア現象」と呼びます。
なぜ逆再生に惹かれるのか
逆再生という行為そのものにも、不思議な魅力があります。
音や言葉を逆にすることで、本来隠されていたメッセージが浮かび上がってくるような感覚を与えるためです。
多くの人はそれを“裏の世界”や“霊的な領域”との接点として捉えがちです。
特に「かごめかごめ」のような、歴史的背景や謎に包まれた歌の場合、その効果はより強くなります。
ただし、このような解釈はあくまで“感じ方”にすぎないという点も大切です。
気をつけたい点
逆再生による解釈は、面白くもありますが、過度に信じ込んでしまうのは避けたいところです。
科学的には偶然の音の重なりや脳の錯覚によって、意味があるように感じてしまうという説明が可能です。
ですから、「怖い」と感じても、現実と空想の境界を見失わないように注意が必要です。
あくまでもひとつの楽しみ方として、冷静な目で向き合うことが大切です。
六芒星と徳川埋蔵金にまつわる都市伝説

「かごめかごめ」と徳川埋蔵金のつながりは、まるで歴史ミステリーのような都市伝説として知られています。
童謡とお宝探しが交差することで、より多くの人の関心を集めてきました。
童謡と六芒星の関係
この伝説の発端は、「かごめ」の語源が「籠目(かごめ)」であるという説にあります。
籠目模様は、竹かごの目のように六角形が組み合わさった形であり、六芒星にも見えます。
そして、この六芒星はイスラエルのダビデの星と同じ形です。
これに関連して、徳川幕府が建立した神社や寺院を地図上で結ぶと六芒星の形になるという話があります。
中心点には日光東照宮があるとされ、そこが埋蔵金のありかではないかという説が語られるようになったのです。
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| シンボル | 六芒星 | 籠目模様と一致するとされる形 |
| 場所 | 中心地 | 日光東照宮が中心に位置 |
| 伝説 | 財宝 | 徳川家の隠された金銀財宝 |
鶴と亀が導くもうひとつのヒント
「鶴と亀がすべった」という歌詞も、徳川埋蔵金説を補強する要素として語られています。
実際に、剣山という場所には“鶴石”と“亀石”と呼ばれる大きな岩が存在し、それが童謡の歌詞と重なるという見方があります。
つまり、歌詞の中の表現が、実際の地形や神話的な要素と結びつけられて、伝説がより具体的なものとして語られているのです。
信じるかどうかは自由だけれど
これまでのところ、徳川埋蔵金が発見されたという確たる証拠はありません。
ですが、こうした話にロマンを感じる人は少なくありません。
童謡という身近な文化と、歴史の奥深さが交差するからこそ、多くの人を惹きつけているのです。
むしろ、現実にはないからこそ想像を広げられるという魅力があります。
「もしかすると本当に…」という想いが、都市伝説を生き続けさせているのかもしれません。
作者不詳の童謡が語る謎と歴史の深淵

「かごめかごめ」は、その作者が誰なのか、はっきりとわかっていません。
これは、単なる忘れられた記録ではなく、民間伝承の文化そのものを映し出している特徴です。
わらべうたの多くは“みんなが作った歌”
わらべうたは、もともと庶民の間で自然に生まれ、親から子へ、子から孫へと語り継がれてきたものです。
そのため、特定の「作詞者」や「作曲者」がいないケースがほとんどです。
「かごめかごめ」も同様に、明確な出典がなく、時代とともに変化しながら歌い継がれてきました。
記録によると、江戸時代の文献にはすでに「かごめかごめ」に近い形の歌が存在しています。
その中では、「つるつるつっぺった」という表現が登場しており、今の「鶴と亀がすべった」とは異なる形で伝えられていたことがわかります。
時代ごとの“解釈の付け足し”
長い年月の中で、歌詞の意味や背景について様々な解釈が加えられてきました。
妊婦の流産説、遊女説、処刑説など、多くの“怖い説”が語られるようになったのも、明確な意図がない分、自由な解釈ができることに起因しています。
こうした背景があるからこそ、「かごめかごめ」は単なる遊び歌以上の存在として扱われるようになったのです。
作者が不明だからこその魅力も
誰が作ったのか分からないということは、言い換えれば「誰でも自由に考えてよい」ということです。
そこに込められた意味を探したり、自分なりの解釈を持ったりできる余地が残されています。
この“余白”があるからこそ、「かごめかごめ」は時代を超えて多くの人に語られ続けてきたのです。
都市伝説が生まれやすいのもその影響といえるでしょう。
何世代にもわたって受け継がれてきたこの歌には、私たちが想像する以上に深い意味や歴史が眠っているのかもしれません。
童謡の世界には、時として大人でも気づかないような謎が隠されているのです。
かごめかごめの歌詞の意味が怖いという事に関するFAQ

- 「かごめかごめ 後ろの正面だあれ」の意味は?
-
「後ろの正面だあれ」という歌詞は、一見すると意味が通じにくく、言葉として矛盾しているように思えます。「後ろ」と「正面」という相反する位置関係が同時に登場しているからです。
この部分は、遊びのルールと密接に関わっています。「かごめかごめ」の遊びでは、中央にいる“鬼”が目隠しをしてしゃがみ、他の子どもたちがその周囲を回ります。歌が終わると鬼が後ろにいる人物を当てるという流れの中で、「後ろの正面だあれ?」という問いかけが使われます。つまりこれは、「自分の後ろ、つまり背後にいる正面の相手は誰?」という意味になります。
古くからのわらべうたにおいては、このような矛盾的表現が意図的に使われることも珍しくありません。子どもが想像力を働かせて楽しめるように、あえて抽象的・詩的な表現になっていると考えられます。
ただし、この一節には「後ろから突き落とした犯人を探している」「処刑された人が自分を取り囲む人々を見ている」など、さまざまな都市伝説的な解釈も存在します。いずれにしても、不思議な言い回しが不気味さを引き立てている要素であることは間違いありません。
- 「かごめかごめ」の歌にはどんな秘密が隠されていますか?
-
「かごめかごめ」には、単なる子どもの遊び歌とは思えないほど多くの謎や秘密が含まれています。実際、この童謡をめぐっては数えきれないほどの解釈や都市伝説が語られてきました。
代表的な説としては、妊婦が流産した悲劇を歌っているという説や、遊女として囚われた女性の心情を描いたもの、さらには罪人が処刑される瞬間を暗示しているという見方まであります。いずれも、歌詞の曖昧さと象徴的な言葉遣いが想像をかき立てるため、多様な解釈が生まれているのです。
さらに興味深いのは、「かごめかごめ」が実はヘブライ語としても読めるとする説です。この考え方では、「かごめ=囲め」などの言葉がヘブライ語と発音・意味の両面で一致し、封印された神宝の存在や火による裁きといった物語に繋がっていきます。
また、「籠目」の形が六芒星(ダビデの星)と一致することから、ユダヤ文化との関連性を指摘する声もあります。こうした背景が加わることで、「かごめかごめ」はただのわらべうたではなく、古代の神話や歴史に通じる“暗号”として語られるようになっているのです。
- 「鶴と亀がすべった」の意味は?
-
「鶴と亀がすべった」という歌詞は、一般的な日本文化において縁起の良い動物である鶴と亀が登場していることから、逆説的にその異変や不吉な出来事を象徴していると捉えられることがあります。
この一節の「すべった」という動詞は、転倒や失敗、あるいは不慮の事故を連想させます。そのため、妊婦が神社の階段で突き落とされ流産してしまったという“嫁姑説”の根拠として、この歌詞が使われることもあります。
一方で、江戸時代に記録された最古のバージョンでは「つるつるつっぺった」となっており、滑るという動作の擬音として使われていたことがわかります。この点から、もともとは物理的な動きを描いた子ども向けの表現だったと考える学者もいます。
ただ、どのような解釈であっても、この一節が不安や不穏な空気を感じさせる要因になっているのは確かです。象徴的な存在である鶴と亀がバランスを崩す描写は、童謡全体に漂う不気味さを一層深める役割を果たしています。
- 童謡かごめかごめの歌詞の意味は?
-
童謡「かごめかごめ」の歌詞は、短いながらも多くの謎を含んでいます。明確な作者は存在せず、口伝えで広がっていったわらべうたであるため、意味や意図については諸説あります。
歌詞の冒頭「かごめかごめ」は、「囲め」という命令形を意味しているという説や、竹かごの目の模様を表しているという説があります。「かごの中の鳥は」という部分は、自由を奪われた存在を指しており、胎児・遊女・罪人など、さまざまな“囚われた存在”の象徴とされています。
「いついつ出やる」は、「いつ出られるのか」という願望や不安を示すフレーズと解釈されており、希望と絶望が入り混じった言葉と見ることができます。
全体を通じて読み取れるのは、「閉じ込められた存在」「外の世界に出られない不自由さ」「後ろにいる誰かの存在を気にする不安感」といった、人間の深層心理を反映したテーマです。単なる子どもの遊び歌とは思えないほど、多層的な意味が込められているのが「かごめかごめ」の特徴といえるでしょう。
かごめかごめの歌詞の意味が怖いが語る深層の背景まとめ
- 「かごめ」は籠の目模様に由来し、六芒星との関連性が指摘されている
- 六芒星の形からユダヤ文化との関係性を示す説も存在する
- 「囲め」という命令形としての解釈は遊び方と一致する
- 「籠女(かごめ)」は遊郭の遊女を暗示する言葉としての意味を持つ
- 「かごの中のとり」は胎児を象徴し、母体から出ることを暗示している
- 「いついつ出やる」は流産や死産を連想させる言葉として解釈されている
- 鶴と亀が滑る描写は吉兆の崩壊を示し、不吉な出来事を象徴している
- 処刑場で罪人が取り囲まれる構図と遊びの構造が類似している
- 「後ろの正面だあれ」は死の瞬間や裁きの恐怖を表しているとされる
- 遊女の閉じ込められた境遇と「かごの中のとり」が重なるとされている
- 口減らしの歴史が子どもたちの遊び歌に反映されているという説がある
- 曲調の明るさと不穏な歌詞のギャップが不気味さを増幅させている
- 意味が曖昧な歌詞表現が想像力をかき立て、怖さを生む要因となっている
- 逆再生により「たすけて」などの声が聞こえるという都市伝説がある
- 作者不詳であることが多様な解釈を可能にし、謎と恐怖を深めている