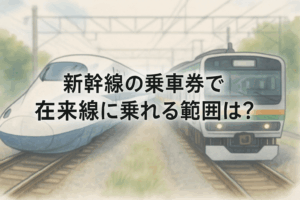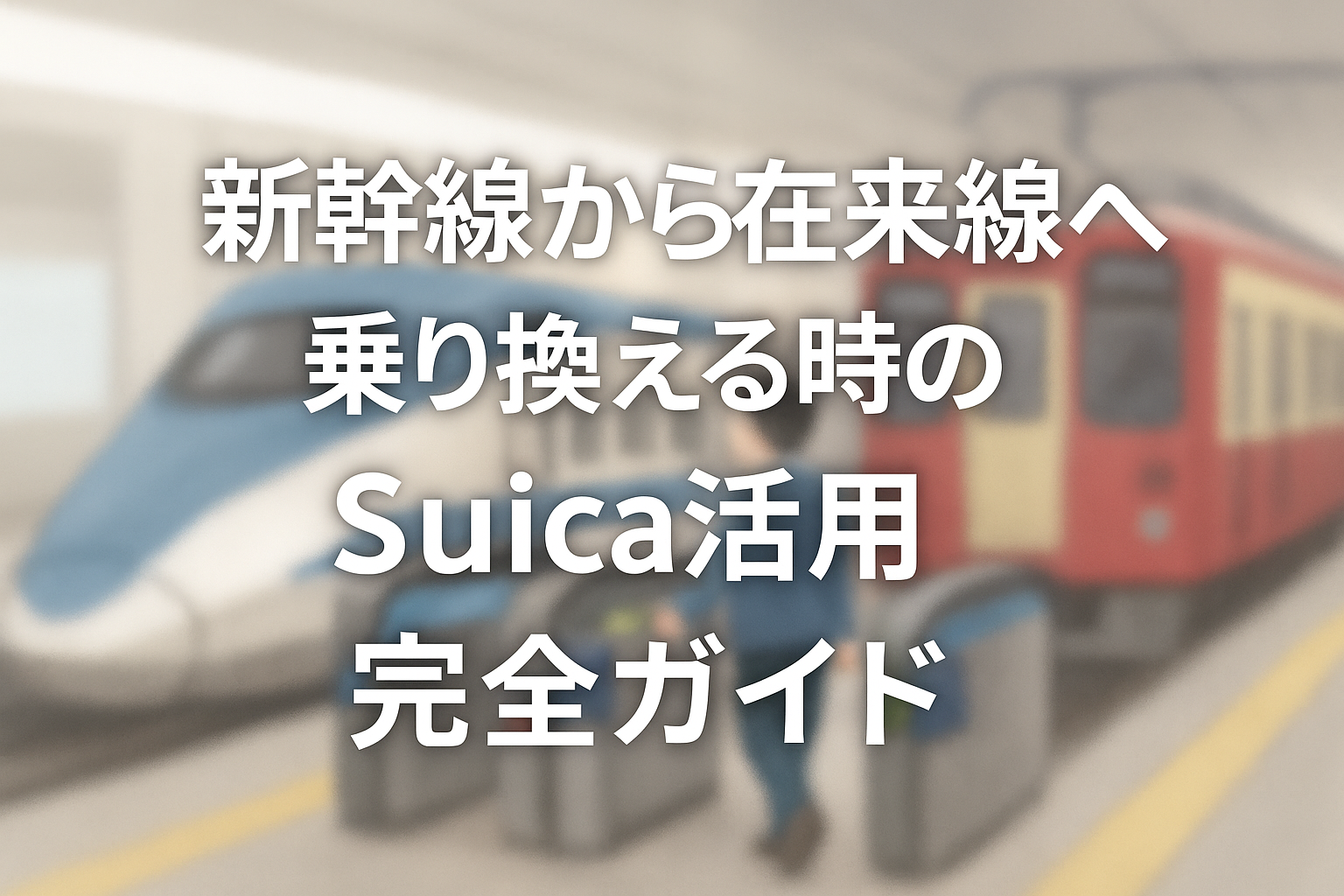新幹線から在来線に乗り換えるとき、Suicaの使い方が合っているか不安になったことはありませんか?
タッチの順番やエリアの違い、モバイルSuicaの操作など、初めての方にとっては戸惑うことも多いものです。
でもご安心ください。
この記事では、「新幹線から在来線 乗り換え suica」の疑問をやさしく解説し、スムーズに乗り換えるための方法や注意点を詳しくご紹介します。
知らないと損をするポイントもあるので、ぜひ最後までご覧ください。
- Suicaを使った新幹線から在来線への正しい乗り換え手順
- 紙のきっぷやモバイルSuicaとの併用方法
- Suicaエリア外や私鉄への乗換時の注意点
- チャージ不足やタッチ忘れなどの対処法
新幹線から在来線へSuicaで乗り換える方法とは

- Suicaで新幹線から在来線にスムーズ移動する方法
- 紙のきっぷとSuicaを併用する乗り換え手順
- モバイルSuica・EX-ICとSuicaの使い分け方
- Suicaエリア外や私鉄乗換の注意点とは
- Suica定期券での乗換可否と利用上の注意点
- Suica利用時のチャージ不足を防ぐポイント
Suicaで新幹線から在来線にスムーズ移動する方法
新幹線から在来線へスムーズに乗り換えるためには、「Suicaを正しい順序で使うこと」が最も重要です。
具体的には、新幹線のきっぷを先に自動改札機へ投入し、そのあとにSuicaをタッチするという流れです。
なぜ順序が大切なのか?
きっぷとSuicaを併用する際、運賃の精算処理はこの操作順によって大きく左右されます。
ICカードを先にタッチしてしまうと、システムが新幹線のきっぷ情報を正しく読み取れず、「ICカードだけで移動した」と認識されることがあります。
このエラーが原因で改札を通過できない、あるいは不要な運賃が引き落とされてしまう可能性もあるのです。
実際の操作手順の一例
例えば、静岡駅から新幹線に乗って東京駅で在来線に乗り換える場合を考えてみましょう。
東京駅の新幹線改札で、まず新幹線の紙のきっぷ(またはeチケットのQRコードがある紙)を入れます。
続けてSuicaをタッチすると、Suicaでの利用区間(例:新宿〜東京)だけが自動で精算され、新幹線区間はきっぷで処理されます。
より快適に乗換えるコツ
改札前で慌てないよう、あらかじめSuicaの残高を確認しておくことも大切です。
チャージ不足の場合は改札を通れないので、改札前に券売機などで補充しておくと安心です。
また、Suicaのタッチ部分が自動改札機のどこにあるかを確認しておくと、よりスムーズに通過できます。
特に混雑する駅では、前の人の操作を参考にしながら動作を確認しておくと良いでしょう。
紙のきっぷとSuicaを併用する乗り換え手順
紙のきっぷとSuicaを併用する際は、乗換改札での操作順がとても大事です。
基本は「紙のきっぷを投入してから、Suicaをタッチ」です。
このルールを守ることで、精算エラーや改札で止められるトラブルを避けることができます。
なぜ順番が重要なのか
この操作順が大事な理由は、きっぷとICカードをシステムが同時に読み取る仕様になっているためです。
ICカードだけを先にタッチすると、新幹線のきっぷが考慮されず、誤ってICカードだけで全区間を移動したと判断されてしまいます。
具体例でわかる使い方
例えば、茅ヶ崎駅からSuicaで入場し、東京駅で新幹線に乗って仙台まで移動する場合、東京駅の新幹線乗換改札では、まず「仙台までの新幹線きっぷ」を投入し、その後「Suica」をタッチします。
すると、Suicaで利用した「茅ヶ崎~東京(都区内)」間だけが自動で精算され、新幹線区間はきっぷでカバーされます。
スムーズな併用のために
Suicaと紙のきっぷを併用する際は、どちらもすぐに取り出せるように準備しておくと、スムーズな通過が可能です。
きっぷをバッグの奥に入れたままにしていると、改札の前で立ち止まってしまい、後ろの人にも迷惑をかけることがあります。
また、ICカードのチャージ残高も事前に確認しておきましょう。
途中駅での乗り越しがあった場合、Suicaでの支払いが必要になるからです。
モバイルSuica・EX-ICとSuicaの使い分け方
モバイルSuicaやEX-ICと通常のSuicaは、それぞれの用途に応じて正しく使い分けることが、スムーズな乗り換えのポイントです。
特にスマートフォンでIC機能を複数使っている方は注意が必要です。
同時使用ではなく「一貫利用」が基本
SuicaとEX-ICなど、異なるICカードを併用してしまうと、自動改札がうまく認識できずに通過エラーが起きる場合があります。
特にモバイルSuicaを使っているスマートフォンには、複数のICカードが登録されていることが多く、意図しないカードが読み取られることもあります。
そのため、乗車から下車までを同じICカードで統一する「一貫利用」が基本となります。
モバイルSuicaの一貫利用例
例えば、モバイルSuicaで新幹線eチケットを予約している場合、在来線の駅でもモバイルSuicaで入場し、乗換駅でも同じモバイルSuicaで新幹線改札をタッチします。
出場時も同じカードを使うことで、スムーズな移動が可能になります。
もし、在来線はSuica、そして新幹線はEX-ICを使ってしまうと、乗換改札でカードが違うと認識され、通過できなくなります。
ICカードを1つにまとめるコツ
スマートフォンに複数のIC機能がある方は、モバイルSuicaをメインに設定しておくと安心です。
設定方法は端末ごとに異なりますが、優先利用するカードを選んでおくことで、改札エラーのリスクを減らすことができます。
また、EX-ICカードなど物理カードを使用する場合は、スマートフォンをタッチエリアに近づけず、カード単体で通過するよう意識しましょう。こうすれば、改札の読み取りエラーも防げます。
Suicaエリア外や私鉄乗換の注意点とは
新幹線から在来線にSuicaで乗り換える際、Suicaエリア外や私鉄線に乗り継ぐ場合は、特に注意が必要です。
スムーズに移動するには、エリアの確認と適切なきっぷの用意が欠かせません。
Suicaが使えない理由と背景
SuicaはJR東日本の交通系ICカードであり、利用可能なエリアは限られています。
一方で、全国のJRや私鉄各社にはそれぞれ異なるICカードエリアがあり、すべての駅でSuicaが使えるわけではありません。
そのため、新幹線を降りたあとに接続する在来線がSuica非対応エリアの場合、ICカードによる精算ができなくなります。
こうした場面では、あらかじめ紙のきっぷを用意するか、乗換駅の改札内にある券売機で在来線のきっぷを購入する必要があります。
よくあるエリア外の乗り換え例
以下に、Suicaが利用できないエリアの一部をご紹介します。
| カテゴリー | 駅名 | 注意点 |
|---|---|---|
| 北海道 | 新函館北斗駅 | 在来線はSuica非対応。きっぷ購入が必要 |
| 北陸地方 | 金沢駅、福井駅 | 在来線はSuica未対応。別途きっぷが必要 |
| 山陰地方 | 鳥取駅など | JR西日本でもSuica非対応の区間が存在 |
このような駅では、新幹線を降りたあと、改札口近くの券売機で在来線用のきっぷを購入しましょう。
券売機の位置がわからない場合や、エリアが曖昧な場合は、駅員に尋ねると確実です。
安心して乗り換えるために
特に初めての駅を利用する際は、事前に「Suica利用可能エリア」の地図や公式アプリで調べておくと安心です。
地図上で確認できる場合もあれば、スマートフォンで「〇〇駅 Suica対応」などと検索すれば、最新の対応状況がすぐに分かります。
万が一Suicaが使えないエリアでタッチしてしまった場合は、改札で止められることがあります。
その場合でも慌てず、近くの係員に説明すれば、適切に対応してくれますのでご安心ください。
Suica定期券での乗換可否と利用上の注意点
Suica定期券を持っている方が、新幹線から在来線に乗り換える際、そのまま使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
実は、定期券の内容や利用区間によって可否が変わってくるため、事前の確認がとても大切です。
定期券だけでは足りないケースも多い
Suica定期券は、あらかじめ決められた区間でのみ利用できる仕組みです。
そのため、定期券の範囲外に乗り越す場合や、新幹線を利用する場合には追加料金が必要になります。
加えて、新幹線は在来線とは異なり、特急料金が別途かかるため、定期券だけでは乗車できません。
たとえば、次のようなケースが該当します。
| 利用例 | 定期券区間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 東京〜大宮間の通勤定期で仙台へ | 東京〜大宮 | 新幹線特急券と乗車券が別途必要 |
| 定期券に新幹線停車駅が含まれる | 郡山〜古川など | 一部条件付きでSuica定期が使える場合あり |
使えるケースもあるが条件が複雑
新幹線停車駅が2駅以上含まれる「Suica定期券」であれば、新幹線を利用できるケースも存在します。
ただし、これはかなり限定されたケースであり、券面表示やICカードの登録状況など、条件が細かく定められています。
また、磁気タイプの「FREX定期券」とSuicaの併用はできないというルールもあるため、ICカードにまとめる方が運用しやすいでしょう。
利用前にやっておきたい確認
以下の点をチェックすると、スムーズな利用につながります。
- Suica定期券の有効区間を確認
- 新幹線停車駅が定期券内に含まれているか
- チャージ残高の有無(特急料金の支払いが必要な場合)
不安がある場合は、みどりの窓口や券売機での照会をおすすめします。
最新のルールに従って案内してもらえるため、安心して利用できます。
Suica利用時のチャージ不足を防ぐポイント
Suicaを使って新幹線から在来線へ乗り換える際、意外と見落としがちなのが「チャージ不足」です。
改札口で引っかかってしまうと、乗り換えが遅れてしまったり、混雑の中で焦ってしまうこともあります。
事前のチャージ確認は、小さな行動ですが大きな安心につながります。
チャージ不足がトラブルの原因になる理由
Suicaは前払い制のカードです。そのため、改札を通る際には利用する運賃分の残高がカードに入っていないと、改札が開きません。
特に新幹線からの乗換駅では、きっぷとSuicaを併用する場合が多く、Suicaの残高不足によるトラブルがよく発生しています。
実際によくあるシーン
例えば、次のようなケースがあります。
| 状況 | チャージ不足の影響 |
|---|---|
| 茅ヶ崎駅からSuicaで入場し東京駅へ | 東京駅の乗換改札でSuica不足により通過できない |
| モバイルSuicaで在来線と新幹線を連携利用 | IC残高不足により在来線改札に入れず再チャージが必要 |
こうしたトラブルは、乗り換え時間の短いときには特に大きな支障になります。
慌てて券売機に戻ったり、駅員に事情を説明する手間も発生します。
チャージ不足を防ぐための工夫
以下のようなポイントを意識すると、チャージ不足を防げます。
- 出発前にSuica残高を必ず確認する
- 予備として500円〜1,000円は余裕をもたせる
- モバイルSuicaならアプリから即時チャージも可能
- 定期的に残高履歴をチェックする習慣をつける
これらの工夫により、乗り換えの際に改札で止められることを避けられます。
特に通勤や旅行での利用時には、スムーズな移動をするためにも残高管理を怠らないようにしましょう。
新幹線から在来線に乗り換える際のSuica利用時の注意点と対処法
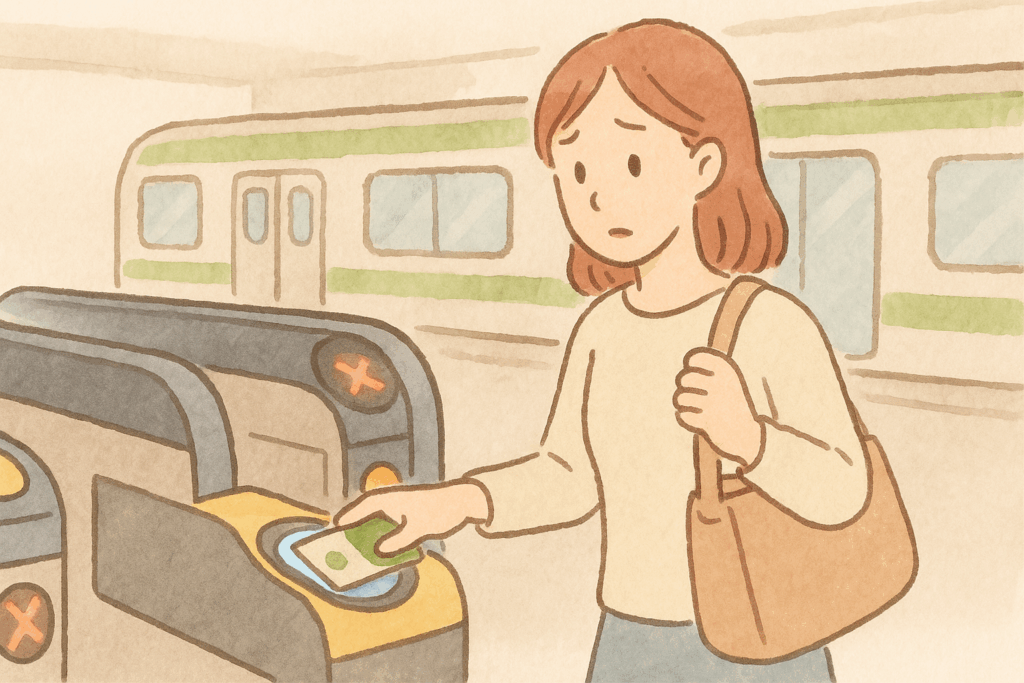
- 新幹線eチケットやスマートEXの連携方法
- Suicaのタッチ手順と改札機の正しい通り方
- ICカードでの乗換時に気をつけたい操作ミス
- Suicaのタッチ忘れ時にすべき正しい対応方法
- 改札で通れないトラブル時の対処マニュアル
- 精算時に使える特定都市区内制度の活用法
新幹線eチケットやスマートEXの連携方法
ICカードとの連携はスムーズな乗車のカギ
新幹線eチケットやスマートEXを使ってチケットレスで乗車するには、事前にICカードとの連携が必要です。
これにより、きっぷの受け取りを省略でき、改札もスムーズに通過できます。
なぜ連携が必要なのか
ICカードを連携していない状態では、改札での認証ができません。
そのため、乗車の予定があっても改札を通れず、結果として電車に乗れないこともあります。
ICカードはチケットの代わりとなる重要な認証手段です。
実際の連携手順について
えきねっとやスマートEXで予約した後、マイページにアクセスして交通系ICカードの番号を登録します。
登録が完了すると、そのICカードが予約情報と紐づき、改札ではタッチするだけで通過できます。
モバイルSuicaを使用する場合も同様に、アプリ内または予約サイトから紐づけ操作を行います。
登録内容を変更したい場合や、ICカードを失くしてしまったときは、再登録や変更手続きを忘れずに行ってください。
再設定をしていないと、新しいカードでは通過できません。
こんなミスにご注意
紐づけ作業をうっかり忘れたまま当日を迎えてしまうと、改札でエラーになり、時間をロスしてしまいます。
また、別のICカードと間違えてタッチすることもあるので、使用するカードはあらかじめ準備しておくと安心です。
Suicaのタッチ手順と改札機の正しい通り方
正しい順序で通ればトラブルなく乗り換え可能
新幹線から在来線への乗換時、Suicaを使う際には操作の順番を守ることがとても重要です。
改札でエラーが出たり、運賃が正しく計算されない原因は、この手順ミスによるものが多く見られます。
きっぷが先、Suicaは後
改札機ではまず新幹線のきっぷ、あるいはeチケットに対応した確認操作を行い、その後でSuicaをタッチします。
この順番が逆になってしまうと、ICカードだけで乗車しようとしたとシステムに認識されてしまい、二重請求や通過エラーが発生する恐れがあります。
この仕組みは、「きっぷ+ICカード」の情報を同時に読み取り、在来線への適切な乗継運賃を計算するために作られています。
そのため、少しでも順番がずれると処理ができなくなってしまうのです。
モバイルSuicaでも手順は同じ
スマートフォンにSuicaを登録している場合でも、操作の流れは同じです。
改札機にスマートフォンをしっかりとタッチし、読み取りが完了してから通過しましょう。
反応が鈍い時は、慌てず一度止まって再タッチすると確実です。
タッチする場所にも注意
改札機には「きっぷ挿入口」と「ICカード読取部」がありますが、それぞれの位置をしっかり確認しておくとスムーズです。
特に混雑時は焦って間違えがちなので、余裕を持って行動することが大切です。
ICカードでの乗換時に気をつけたい操作ミス
小さなミスが大きなトラブルに
ICカードでの乗換はとても便利ですが、ちょっとした操作ミスが大きなトラブルにつながることもあります。
これを防ぐには、正しい使い方を事前に把握しておくことが大切です。
よくある3つのミス
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| タッチエラー | 複数ICカードの同時タッチ | SuicaとPASMOなどを財布に入れたままタッチすると、読み取りできずエラーになります。 |
| カード切り替えミス | 在来線と新幹線で別のICカードを使用 | 新幹線用に紐づけたICカードで入場しないと、改札を通れません。一度出場が必要になります。 |
| 改札通過忘れ | 改札を通らずに直接ホームへ | 正規のルートを通らないと、不正乗車とみなされることがあります。 |
こうすれば防げます
複数のICカードを使う予定がある場合は、あらかじめ使うカードを1枚に絞っておくことが効果的です。
財布やスマートフォンケースの中でカードが重ならないように管理しましょう。
また、新幹線用のICカードと在来線用のカードが異なる場合は、必ず新幹線乗車前に一度在来線改札を出てから入り直す必要があります。
この手間を避けたいなら、1枚のICカードで統一するのがベストです。
ICカードはとても便利なツールですが、使い方を間違えると逆に不便になってしまうこともあります。
安心して移動するためにも、事前の準備と確認を忘れずに行いましょう。
Suicaのタッチ忘れ時にすべき正しい対応方法
新幹線から在来線に乗り換える際、Suicaをタッチし忘れてしまった場合でも、落ち着いて対応すれば問題ありません。
焦らず正しい行動をとることで、スムーズに処理を進めることができます。
改札でエラーが出たときの基本対応
タッチ忘れに気づく場面として多いのが、乗換改札や降車駅の自動改札での「エラー表示」です。
このときは無理に通過しようとせず、その場で立ち止まりましょう。
改札には駅員呼び出しボタンがありますので、それを押して係員を呼んでください。
駅員に「タッチし忘れてしまった」旨を伝えると、事情を確認した上で、正しい精算処理や通過対応をしてくれます。
無理に通り抜けようとすると不正乗車とみなされる恐れがあるため、必ず係員に説明しましょう。
紙のきっぷとSuicaの併用時にありがちなミス
例えば、新幹線のきっぷを自動改札に入れたあと、Suicaをタッチするのを忘れた場合、改札が開かず立ち往生してしまうことがあります。
このようなときは「きっぷは入れたが、ICカードのタッチを忘れた」と伝えることで、手動での通過処理を受けることが可能です。
モバイルSuicaの場合の注意点
スマートフォンでモバイルSuicaを使用している場合、画面がオフになっている、またはアプリが正常に起動していないと読み取りに失敗することがあります。
改札通過後に「実は反応していなかった」と気づくこともあるでしょう。
このような場合も、駅係員に申し出ることで履歴を確認し、必要な精算や記録の修正をしてもらえます。
スマホの反応が鈍いと感じたら、あらかじめ再起動する、アプリを開いておくなどの対策が安心です。
改札で通れないトラブル時の対処マニュアル
改札で止められてしまうと誰でも焦ってしまいますが、トラブルの原因を把握すれば冷静に対応できます。
ここでは、Suicaを使った際にありがちなエラーとその対処法について説明します。
よくあるエラー表示と原因
改札で通れないときに表示される主なエラーは、以下のようなものがあります。
| カテゴリー | 表示内容 | 原因の例 |
|---|---|---|
| チャージ不足 | 残高不足です | Suicaの残額が初乗り運賃に満たない |
| 読み取り失敗 | 再タッチしてください | タッチが弱かった、モバイルSuicaの不具合 |
| 入出記録エラー | 入場記録がありません | 乗車時にタッチを忘れた、エリア外から乗車 |
このような表示が出た場合は、案内のとおり再タッチを試してみて、それでも通れないときは駅係員のいる改札口へ向かいましょう。
駅係員によるサポート内容
駅員のいる窓口では、Suicaの利用履歴を専用端末で確認し、不足分の運賃をその場で精算してくれます。
また、タッチ忘れや乗越しなどのイレギュラーなケースも、状況に応じて処理してくれます。
Suicaでの改札通過ができなかったからといって不正扱いにはなりませんので、安心して相談して大丈夫です。
トラブルを防ぐための事前対策
このようなトラブルを避けるには、以下の点を確認しておくと安心です。
- Suicaに十分なチャージがあるか
- モバイルSuicaの動作確認(電池残量・アプリ起動など)
- 改札機の案内表示をよく見る
- ICカードを1枚のみにして、重ね持ちは避ける
特に、モバイルSuicaはスマートフォンの状態に依存するため、朝の通勤前などに一度タッチの反応を確認しておくと良いでしょう。
精算時に使える特定都市区内制度の活用法
特定都市区内制度は、新幹線や在来線を長距離移動する際に役立つ運賃制度です。
この仕組みを理解しておくことで、余計なきっぷを買わずに済み、スマートな移動が可能になります。
特定都市区内制度とは
この制度は、200km以上の距離を移動する乗車券に限り、「東京都区内」「大阪市内」などの特定の都市エリアを1つの駅として扱う仕組みです。
対象のエリア内であれば、どの駅から乗っても・降りても追加料金はかかりません。
制度が使える具体的な例
以下のような乗車券では、制度を活用することができます。
| 出発地 | 到着地 | 対象エリア | 使い方 |
|---|---|---|---|
| 茅ケ崎駅 | 大阪駅 | 東京都区内・大阪市内 | 「東京都区内→大阪市内」のきっぷで、茅ケ崎から在来線→東京→新幹線→大阪のルートをカバー可能 |
| 鎌倉駅 | 仙台駅 | 東京都区内・仙台市内 | 同様に、エリア内移動は新たにきっぷを買わずにOK |
これにより、在来線から新幹線に乗り換える際、東京都区内の駅であればどこからでも出発できることになります。
注意点と使う前の確認ポイント
便利な制度ですが、いくつかの注意点があります。
- 対象となるのは200km以上の乗車券に限られること
- 特定都市区内を出ると、制度の対象外になる
- 途中下車すると再入場はできない
また、きっぷを購入する際に「〇〇市内」と記載されているかを必ず確認してください。
制度を使いたい場合は、みどりの窓口や券売機で出発地・目的地を正確に指定する必要があります。
この制度を理解していれば、無駄な精算を避けるだけでなく、旅行や出張の計画も立てやすくなります。
適切に活用すれば、移動コストの節約にもつながるでしょう。
新幹線から在来線にSuicaで乗り換える際のFAQ(よくある質問)
- 新幹線から在来線に乗り換える時のSuicaの精算方法は?
-
新幹線から在来線に乗り換える場合、Suicaの精算は降車駅で行います。Suicaを使用して新幹線に直接乗車したわけではないため、精算処理が必要となるのは在来線の下車時です。
なぜなら、新幹線と在来線では運賃体系や利用方法が異なり、Suicaの自動精算は在来線の区間にのみ適用されるためです。
例えば、紙のきっぷや新幹線eチケットで新幹線に乗り、在来線にSuicaで乗り継いだ場合、下車駅の「のりこし精算機」や改札窓口で精算する必要があります。この際、Suicaをタッチして精算金額を確認し、チャージ残高から自動的に支払いが完了します。
一方、乗車前にきっぷを購入している場合でも、Suicaで区間外に乗り越したときは同じように精算が必要です。
つまり、Suicaは在来線利用分の精算に使うものであり、新幹線区間の料金は別に支払われている点に注意しましょう。
- 新幹線から在来線に乗り換えるときSuicaはどちらを先に通?
-
Suicaときっぷを併用して乗換改札を通る場合、必ずきっぷを先に通してからSuicaをタッチしてください。
これはシステム上の仕様であり、ICカードを先にタッチしてしまうと正確な運賃が計算されない恐れがあるからです。
例えば、新幹線の改札で紙の乗車券を入れずにSuicaを先にタッチすると、システムはSuicaだけでの利用と判断してしまい、新幹線の料金を二重で請求されることがあります。このようなトラブルを避けるためにも、順番はとても重要です。
そのため、乗換改札では「きっぷを入れてからICカードをタッチする」という流れを覚えておくと安心です。
- 新幹線から在来線に乗り換える時はどうすればいいですか?
-
新幹線から在来線に乗り換える場合は、「新幹線乗換改札口」を通って、きっぷとICカードの両方を適切な順序で操作する必要があります。
乗換改札には、新幹線のきっぷ(もしくはeチケット)を挿入し、その後にSuicaなどのICカードをタッチします。順番を間違えると、改札が開かないことや料金トラブルが発生することがあるため注意が必要です。
例えば、東京駅で新幹線を降りてSuicaで在来線に乗る場合、新幹線乗換改札に向かい、持っている新幹線のきっぷを入れてからSuicaをタッチすることで、きっぷでカバーされていない区間の運賃をSuicaで支払えます。
この操作を間違えずに行うことで、スムーズに在来線に乗り換えることが可能になります。
- モバイルSuicaで新幹線から在来線に乗り継ぐことはできますか?
-
モバイルSuicaでも、新幹線から在来線への乗り継ぎは可能です。ただし、新幹線eチケットサービスと事前に紐づけておく必要があります。
この紐づけをしておけば、モバイルSuica1枚で新幹線の改札と在来線の乗り換え改札の両方を通過できます。紙のきっぷを持つ必要がないため、チケットレスでスムーズな移動が実現します。
例えば、新宿から東京まで在来線を利用し、東京から仙台まで新幹線で移動する場合、モバイルSuicaを使用して在来線に乗り、東京駅では新幹線乗換改札をモバイルSuicaでタッチするだけで乗車可能です。
ただし、モバイルSuicaにチャージが不足していた場合は、改札を通れないため、事前のチャージ確認は欠かせません。また、在来線と新幹線で別のICカードを使用しているとスムーズな乗継ができないため、1枚のICカードに統一しておくことも重要です。
新幹線から在来線に乗り換える時のsuicaの基本ルールと実践ポイントまとめ
- 新幹線改札ではきっぷを先に入れてからSuicaをタッチする
- Suicaは在来線区間の精算にのみ使われる
- チャージ不足だと改札を通過できないため事前確認が必要
- モバイルSuicaも利用可能だがICカードの紐づけが必要
- 複数ICカードの重ねタッチはエラーの原因となる
- 新幹線eチケットとSuicaは事前に連携しておく
- 紙のきっぷとSuica併用時は順番ミスに注意
- Suicaエリア外ではICカードが使えないためきっぷ購入が必要
- 在来線との乗換時は新幹線乗換改札を使う
- 定期券は区間内でのみ利用可能で新幹線には使えない場合が多い
- 特定都市区内制度を活用すればきっぷ1枚で移動できる場合がある
- 誤タッチやスルーした際は駅員に申告すれば対応可能
- モバイルSuica利用時はアプリの動作確認も忘れずに行う
- EX-ICとSuicaを併用する際はカードの使い分けに注意する
- 乗車から下車まで同一ICカードで統一するのが基本